注目市場の一つはインド
第334回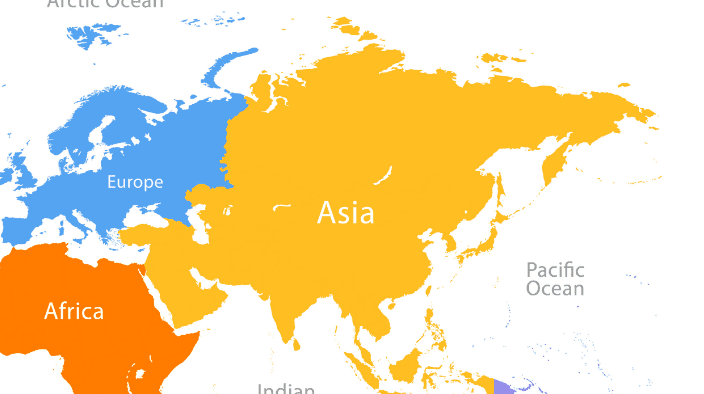
今世界的に「次の有望な投資市場」との見方が強まっている国がある。インドだ。2023年内には人口で世界一になると見込まれる。中国越え。かつ、自他ともに認めるグローバル・サウスの指導的国家であり、米ソ・米中対立の先鋭化の中で、国際的スタンディング(立ち位置)は「有利」になっている。今後ますます世界での優位性が際立つと予想される。
インド出身経営者がいくつかの米IT企業のトップを占めていることは、よく知られている。加えてインドは世界的な指導者を他国で次々に生み出している。代表は英国のスナク首相で、米国のハリス副大統領もそう。次期米大統領選挙の共和党候補者の中には「インド系」が2人もいる。実業家であり保守派の評論家としても知られるビベック・ラマスワミ氏(37)とニッキー・ヘイリー元国連大使(51)。
中国との違いは明確だ。2024年の大統領選挙候補者の中に有力な中国系はいない。米国のインドとの距離感は、中国に比べて極めて近い。米国はまたインドを中国のように「自国にとっての競争国・競合国」とは見なさず、むしろ協調・協力を望む。こうした環境は、インドが今後も世界の政治・経済においてパワーを存分に発揮するであろうことを予感させる。
中国は世界の資金の流れの中で、自らを隔離しようとしているように見える。力のある企業や個人の台頭を、共産党一党体制(習近平体制)への脅威として抑止しようとする「共同富裕」の考え方を基本理念とする。また海外企業の中国国内での経済・社会活動に懸念を抱かせる「改正反スパイ法」も施行した。
世界の投資家にとって頭から離れない究極のリスクは、中国による「台湾への武力侵攻の可能性」だ。それを中国自身が示唆している現状では、世界のマネーが中国に大規模に向くことは当面無理だ。李強首相は自ら欧州に足を運んで世界の投資家に「中国は懐の深い国」と対中投資を呼びかけている。しかし実際にやっていることは、カナダや日本企業の駐在員のスパイ容疑での逮捕だ。その行動は不穏で、ヒト、モノ、カネの流れを自ら止めているように見える。
戦略的な立ち位置の有利さ
対してインドの国際的立ち位置は驚くほど良い。他の国に対しては「人権」を声高に外交政策の柱に押し出す米国さえも、インドが持つ地政学的な立ち位置の重要性やユニークな歴史(非同盟主義を貫徹)故に、その外交姿勢の適用を躊躇(ちゅうちょ)している。
米国にとっては、インドをどうしても「我が仲間」に引きつけておく必要がある。国際政治面での優位性を確保するためだ。中国、ロシアと対立する中ではどうしてもそうなる。逆に、ロシアや中国もインドの支持が欲しい。結局インドには、米国も含めてどの国も歯にものが挟まったような指摘しか出来ないのだ。
米国国内に根強くあるインド批判の一つは、人口の一割程度いるとされるイスラム教徒の扱いだ。インドは「ヒンズーの国」とされる。それは人口の大部分がヒンズー教徒だからだ。英国の植民地だった南アジアのエリアがインドとパキスタンの二つの国に割れる段階で、今のインドエリアに居た多くの余裕のあるイスラム教徒はパキスタンに逃れたとされる。そのため、インドに残ったイスラム教徒は総じて貧しかったようだ。それもあってインドでは、イスラム教徒迫害の事例が後を絶たない。インドの人権問題の一つだ。
しかしバイデン大統領は最近、インドのモディ首相を同盟国以外の国から初の国賓として米国に招き、特別待遇を示した。記者からインド国内のイスラム教徒が置かれた状態に関して質問を受けた際には、質問をかわして、米国にとってのインドの重要性を指摘したにとどまった。人権外交がウリの米民主党政権にしてそうなのだ。
インドが中国を抜いて世界一の人口(14億人を超える)を抱える国になるということも重要だ。インドは筆者が何回も訪れた2005年から07年にかけてようやく消費社会が芽吹いてきていた。筆者が「ITとカーストインド・成長の秘密と苦悩」(日本経済新聞社)という本を書いたのはその2007年。中国は改革開放の名の下に、もっと早くから経済の発展に舵(かじ)を切っていた。経済発展においては、インドは中国の後を追う国だった。
成熟に向かう消費市場
それから15年以上。今インドでは中間層が拡大し、内需主導の成長への期待が高まっている。売れる車にその顕著な変化が見える。『バイクに家族全員乗車→小型車マルチでの家族移動』の時期を経て、今インドでは比較的サイズの大きい多目的スポーツ車(SUV)が車販売のかなりの部分を占めるようになっている。これは大きな変化だ。
車だけではない。世界にIT技術者を多く輩出している国として、インドでは比較的高い所得のサラリーマン層が厚くなり、それが家電、衣類、住居などを含めて「高級品・ブランド市場の成長」につながっている。それはインド市場でビジネスをする企業の業績を押し上げる。例えば同国自動車市場でシェアトップを占めるマルチ・スズキが4月末に発表した決算では、売上高と純利益がともに史上最高だった。
日本人にもおなじみの米アップルは、インドを製品販売のみならず、製造基地として重視し始めた。同社は今年4月に商都ムンバイに同社としてインド初のアップルストアをスタートさせた。これは日本でも報じられたが、同社はそれに加えて生産面でも「インド重視」の姿勢を示す。アップルは今まで中国を一大生産基地としてきた。その方針を変えつつある。またアップル製品も組み立てで知られる台湾の鴻海精密工業もインドでの生産拡大の方針だ。
世界を鳥瞰(ちょうかん)したとき、インドは「国内での成長余力が極めて大きい市場」との見方が定着しつつある。行くとすぐ分かるが、とにかく14億の人口構成が極めて若い。若者は購買意欲が旺盛で、しかも彼らの中にはITに強い優秀な労働者が数多くいる。彼らは米IT企業のトップを継ぐ人材になり得るだろうし、インドの勤労者の平均所得を押し上げるだろう。インドは今後10年の世界を考えると、最も成長余力の大きい市場と考える事が可能だ。
パラドックス的優位
インドの地政学的有利さを具体的に言うと、「いいとこ取り」が出来るということだ。ウクライナ侵攻によるロシア産の資源に対して日本など西側諸国が制裁を科す中で、インドは引き取り手のなくなったロシア産の石油・天然ガスを大規模に、しかも安値で入手できる立場となった。それをよく思わない西側諸国は多いが、それを理由に強く非難することはインドの西側からの離反を招く恐れがある。
多分、現在の環境は続く。なぜならインドは世界一の人口(消費者)を抱える大きなマーケットであり、同時に高成長国だ。加えて世界の大勢が権威主義国優位に傾くか、それとも西側民主市議陣営優位に傾くかのカードを握っているからだ。実はインドは「世界最大の民主主義国」と呼ばれるが、その世界における立場は微妙だ。
民主主義国だが、かつては英国の植民地。英国など旧宗主国側の欧米には違和感や反感を持つ。中国とは隣国だが、国境紛争を抱える。また「中国人はカレーを食べない」(友人の中国人の言葉)と言い切るほど、文化的な相違がある。そう言えば、何回も旅したが世界中にあるはずの中華料理屋が、インドでは極めてまれだった。逆も同じ。つまりインドと中国は味覚でも反りが合わないのだ。
インドは武器などの入手を西側でもなくソ連、その後のロシアに頼ってきた。今でもそうで、それがウクライナ侵攻を見てもインドが「ロシアの友好国」の立ち位置から決別できない背景となっている。今は米国との武器の共同生産などの構想を打ち出しているが、インドが完全に米国側に舵を切ることは当面ないだろう。
どの主要国とも一定の距離を置くインド。しかしそれが今は世界におけるインドの「相対的優位性」につながっている。パラドックスと言える。相対的優位性故に、世界一の人口国・インドは、当面は投資の世界においても「有望な国」であり続けるだろう。